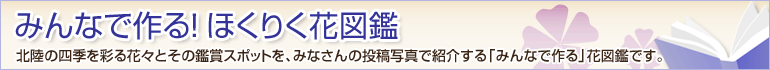
参考資料:いしかわ樹木図鑑、自然人第2号、栂 典雅 著「白山・花ガイド (改訂版)」
一覧から探す
全136件
アオノツガザクラ<青の栂桜>
高さ7~15cm、花の長さは約7mmの壺形で下向きにつきます。葉がツガ(モミの仲間)に似ていることが名の由来。
アケボノスギ<曙杉>
落葉高木。和名はアケボノスギだが、通常はメタセコイアの名で呼ばれることが多い。スギ科の針葉樹でありながら黄葉して落葉する。化石から太古の日本にはたくさん生育していたことがわかったが今は絶え、近年、中国四川省で生き残っていることが発見されて、「生きている化石」と称される。街路樹や公園に植樹されて広まった。
アケボノソウ<曙草>
高さ60~90cm、花径は2cmほど。花びらの先の方に斑点があり、これを明け方の星に見立てたところから名づけられました。
アジサイ<紫陽花>
高さ1~1.5m、花びらに見えるものは萼です。一般に植えられている球状のアジサイはセイヨウアジサイであり、日本原産のガクアジサイが改良された品種です。
アズマシロガネソウ<東白銀草>
高さ10~25cm、花の直径は7~10mmほど。やや日陰の湿ったところに生える多年草です。
アナマスミレ<アナマ菫>
高さ7~8cm、花径2cmほど。葉は細長くやや内側に巻いています。礼文島の西海岸のアナマで発見されたことにより名付けられました。
イソスミレ<磯菫>
高さ5~10cm、花径2cmほど。葉は心形で厚く、光沢がある。生育地が極端に減っているため、保護が必要と言われています。 別名:セナミスミレ。
イタヤカエデ<板屋楓>
山地に生える落葉高木で樹高20m、直径1mに達する巨木となり、サトウカエデのように樹液を集めて煮詰めるとメープルシロップができる。アカイタヤ、ウラジロイタヤ、オニイタヤなど亜種がいくつかあり、イタヤカエデは総称的な名前と なる。
イチョウ<銀杏>
中国原産の落葉高木。裸子植物の一種。移植により世界中に分布しており、街路樹や公園に多く、もっとも身近な黄葉する木のひとつ。
イロハモミジ<いろは紅葉>
日本でよく見られるカエデ属の落葉低木で、紅葉の代表種。イロハカエデ、単にカエデやモミジとも呼ばれる。北陸では概ね標高200m以下の山地に分布する。葉の幅は2~7cm。
イワウチワ<岩団扇>
高さ5~15cm、花径2.5~3cm。葉は厚く光沢があり、形が団扇に似ていることから名がつけられたようです。 別名トクワカソウ。
イワオウギ<岩黄耆>
高さ20~70cm。花は長さ約1.5cm。10個以上の花が下向きに集まってつきます。黄耆は中国産の薬草。白山黄耆の名で古くから薬用にされたのは、本種と思われます。別名:タテヤマオウギ。
イワギキョウ<岩桔梗>
高さ5~10cm、花は釣鐘型で長さ約2.5cm。青みがかった紫色で無毛です。
イワショウブ<岩菖蒲>
高さ15~50cm、花径約1cm。花の先端が紅色をおびるものもあり、茎の上部が粘ります。名は岩に生えるショウブの意ですが、ショウブはサトイモ科。
ウスユキソウ<薄雪草>
高さ10~20cm。花びらに見えるのは苞葉です。名は白い綿毛をかぶった姿から。エーデルワイスはこの仲間です。別名:ミネウスユキソウ。
ウメ<梅>
バラ科サクラ属の落葉高木。白・淡紅・紅色など、葉より先に香りの強い花を咲かせ、実は6月ごろに熟します。中国の原産で、古くから庭木などに重宝され、品種は300を超えるといわれます。ちなみに、サクラの花との見分け方は、花柄の長いサクラと比べ花柄のないウメは枝に直接花がついているように見えます。また、花弁(花びら)の先はサクラは割れ、ウメは丸いのが特徴です。
ウメバチソウ<梅鉢草>
高さ10~30cm、花径1.5~2cm。5個の仮雄しべの先端が9~22裂して、先端に小さな玉がつきます。葉は1枚茎につき、柄はありません。花が梅鉢の紋に似ていることが名の由来です。
ウリカエデ<瓜楓>
落葉小高木で、別名はメウリノキ。葉は浅く3~5裂する。石川県を例にすると中能登以南の標高800m以下の山地に分布。葉の幅は2~7cm。葉の形が似たウリハダカエデと比べ葉の大きさが小さい。
ウリハダカエデ<瓜膚楓>
落葉高木で、樹皮の模様の色がマクワウリの未熟な実の色に似ていることからこの名がついた。加賀ではウリノキ、アオハダなどとも呼ばれる。ブナクラス域以下の山地に分布。葉の幅が7~20cm。
ウンラン<海蘭>
草丈10~30cmほど。海岸の砂地に生える多年草。浜辺に生えて、蘭に似た花をつけることから命名されました。北海道・本州・四国に分布します。
エゾタンポポ<蝦夷蒲公英>
このタンポポは北海道と本州の中部以北に分布する在来種で、帰化種のセイヨウタンポポのように頭花の下の総苞片は反り返っていません。在来種は帰化種より繁殖力が弱く、また帰化種と在来種の自然交雑種が増えているとの報告もあり、純粋なエゾタンポポは数を減らしているようです。多年草で草丈は20~30cm。
オウレン<黄連>
里山や低山の林床に多く生える多年草で、別名はキクバオウレン。根茎は苦味健胃、整腸、止瀉等の作用があり、生薬として用いられます。北陸ではこのキクバオウレンが一般的ですが、とてもよく似たセリバオウレンも見かけるようです。
オオイヌノフグリ<大犬の陰嚢>
越年草で、道ばたや畦道など、どこでも見られるヨーロッパ原産の帰化植物。花弁は4枚あり、花は左右対称。近縁のイヌノフグリもかつて身近な存在でしたが、オオイヌノフグリに駆逐されて、現在で絶滅危惧種となってしまいました。
オオカメノキ<大亀の木>
落葉低木・小高木。別名はムシカリで、葉を虫が好むことから。他の木に先駆けて紅葉する。主にブナクラス域に生育するが、虫食いだらけの葉が目立つ。葉の幅は7~20cm。
オオバタケシマラン<大葉竹縞蘭>
高さ50~80cm。花径約1.5cmで花被片が反り返る。葉のつけ根から1個ずつぶら下がり、柄がねじれるのが特徴です。葉は裏が白く、葉茎を抱く。
オオヒョウタンボク<大瓢箪木>
高さ1~2mの落葉低木。花は長さ5cmの花柄の先に2個ずつ横向きにつきます。実は径約8mmで、2個がくっつき赤く熟します。有毒。名はこの実を瓢箪に見立てたもの。
オオレイジンソウ<大伶人草>
高さ0.5~1m。花はたての長さ約2.5cm。名の伶人とは雅楽を演奏する人のことで、花の形が伶人の使う冠に似ていることから。有毒。
オタカラコウ<雄宝香>
高さ0.7~1m以上、頭花の径約4cm。花びらに見える舌状花は5個以上、葉は丸みのある心形で幅20cm~40cmです。標高の低いところでは高さ2mに達します。
オヤマリンドウ<御山竜胆>
高さ20~50cm、花径約2.5cm。晴天時でも先はやや開く程度。名の御山は白山を指すとされています。
オンタデ<御蓼>
高さ0.3~1m、花径約4mmの小花が円錐状の花序をなします。雄株は花が終わると花序が赤みをおび、長さ1cmの翼のある実がなります。葉は卵形で先がとがっています。
カタクリ<片栗>
高さ10~15cm、花径4~5cm。薄紫・紅色の花を斜下向きにつけます。まれに白色の花を咲かせることもあります。
カツラ<桂>
落葉高木。ハート型の愛らしい葉っぱで、秋になると鮮やかな黄色に色づきキャラメルのような香りがする。主にブナクラス域に分布するが、街路樹や公園などでもよく目にする。葉の幅は2~10cm。
カライトソウ<唐糸草>
高さ30~70cm、花序は長さ6~10cmの円柱形で垂れ下がり、花は花序の先から順に咲きます。繊細で美しい雄しべのさまを中国渡来の絹糸に例えたのが名の由来です。
カラマツ<唐松>
落葉高木。マツ科の針葉樹でありながら鮮やかに黄葉して落葉するのが珍しい。紅葉の時期は他の木々よりも遅い。中部山岳地帯の山地帯から亜高山帯などに分布するが成長が早いことから植林にも利用される。
カラマツソウ<唐松草>
高さ0.4~1m、花径約1cm。4、5枚ある萼片は早くに落ち、花弁もありません。円形に開出する白い糸状のものは、雄しべの花糸であり、これがカラマツの芽吹きに似ていることが名の由来です。
キオン<黄苑>
高さ0.3~1m、花径約2cmの頭花が集まって付きます。舌状花は5、6個。葉は鋸歯が目立ち、葉柄はないか、ごく短いです。
キクザキイチゲ<菊咲一華>
高さ10~20cm、花径3cmほど。花弁に見えるのは萼片で8~13枚あります。
キヌガサソウ<衣笠草>
高さ30~70cm、花径約6cm。花びらのように見えるのは萼片。初めは白いが、紅紫色になり、実が熟する時期には淡緑色に変わります。葉は8~12枚が輪生します。
クサボタン<草牡丹>
高さ0.5~1m、花は筒状の釣鐘形で長さは1.5m~2cm。花弁ように見えるのは萼で先が4裂し反り返ります。葉は3小葉からなる複葉で、縁は粗い鋸歯のようになっています。葉が同科のボタンに似ているのが名の由来です。
クルマユリ<車百合>
高さ0.3~1m、花径約5cm。茎の中ほどで数枚~10枚以上の葉が輪生します。名はこの葉を車輪に見立てたもの。
クロユリ<黒百合>
高さ10~25cm。花は長さ約3cm。白山を代表する高山植物で、昭和29年に石川県の「郷土の花」に選ばれました。別名:ミヤマクロユリ。
ケヤキ<欅>
落葉高木。低山や里山に多く分布するが、街路樹などにもよく使われる。紅葉は美しく、赤や黄色に紅葉する。木目がはっきりとして狂いの少ない材は高級な家具や建材として利用される。葉の幅は2~7cm。
ゲンゲ<紫雲英>
中国原産の越年草で、レンゲソウ(蓮華草)やレンゲとも呼びます。もともと水田で緑肥として栽培されており、一時はかなり減りましたが、ゲンゲを緑肥にした有機栽培米が注目され、あちこちの水田で散見できるようになりました。良質な蜂蜜をもたらす蜜源植物としても知られています。
ゲンノショウコ<現の証拠>
多年草で茎は約30~40cmまで伸び、紅紫色または白紫色の花が咲きます。紅紫花種は西日本に、白紫花種は東日本に多く見られるそうです。ドクダミ、センブリなどと共に、江戸時代から民間薬として用いられ、植物名は「胃腸に実際に効く証拠」を意味し、イシャイラズの異名もあります。
コシアブラ<漉油>
樹高10mほどの落葉高木。葉は掌状複葉で5枚の小葉からなります。頂小葉がいちばん大きく、長さ10~20cm、幅4~9cm。紅葉は透明感のある白色になり、赤や黄色の葉の中ではよく目立ちます。
コハウチワカエデ<小羽団扇楓>
落葉高木で別名はイタヤメイゲツ。主にブナクラス域に分布する。葉の幅は2~7cmとハウチワカエデに比べると小さい。
コバイケイソウ<小梅蕙草>
高さ0.5~1m、花径約1.5cm。雄しべは花被片より長い。花序は丸みをおび、ふつう中心の穂は両性花、側枝の穂は雄花からなります。有毒。
コブシ<辛夷>
マンサクやタムシバと同様、北国に春の到来を告げる花として知られます。野山に咲くモクレンに似た花はコブシと思われがちですが、北陸ではタムシバの方が多く、実はコブシは少数派。里山の山裾や山腹などに多く、通常、タムシバよりも高木になり、20m近くになることもあります。別名:キタコブシ。
コマツナギ<駒繋>
落葉小低木で、樹高60~80cmほど。本州、四国、九州で、海岸や道ばた、野原など、日当たりのよい乾いたところに生えます。馬の手綱を結んでも抜けないほど丈夫なことからその名がついたそうです。
ゴゼンタチバナ<御前橘>
高さ5~15cm、花径約2cm。4枚の花びらに見えるのは総苞片で、本当の花は中心に集まる小花です。
サクラ<桜>
ササユリ<笹百合>
高さ30~70cm、花は長さ約10cm。ほとんど白に近い淡紅紫色から色の濃いものまであり、強い芳香があります。名の由来は、葉がササの葉に似ていることから。
サザンカ<山茶花>
寒い時期に花を咲かせます。野生種の花の色は部分的に淡い桃色を交えた白ですが、園芸品種の花の色は赤や白、ピンクなどさまざま。ツバキによく似ていますが、花弁が1枚1枚散るのが大きな違い。
サンカヨウ<山荷葉>
山地帯から亜高山帯のやや湿った場所に生える多年草ですが、白山では高山帯でも見られます。高さは30~60cm。花径2cmほどの白色の花が茎の上部に集まってつきます。青紫色で白い粉を帯びた実をつけ、実は食べられます。
シナノオトギリ<信濃弟切>
高さ10~30cm。花径約2cm。葉は対生し、透かして見ると縁に黒点、葉面に明点があります。
シモツケソウ<下野草>
高さ30~80cm、径約5mmの小花が茎の上部に密集します。葉は奇数羽状複葉ですが、側小葉は目立たず、頂小葉は掌状に3~5裂しています。
シャガ<射干>
中国原産でかなり古くに日本に入ってきた帰化植物と考えられています。杉林の林床など山野の湿ったところを好み、また、人の影響の少ない自然林内にはあまり自生しません。白っぽいアヤメに似た直径5~6cm程度の花を花茎の先に咲かせます。
シャリンバイ<車輪梅>
海岸にある日当たりの良い岩の上などによく見られ、ウメによく似た花を咲かせます。よく似たものに葉が幅広く倒卵形の「マルバシャリンバイ」、葉の幅が狭い「タチシャリンバイ」がありますが、中間型もあって区別が難しい。常緑低木。庭木や道路脇などに植栽されることも多いです。
シュンラン<春蘭>
土壌中に根を広げる地生蘭の代表的なもので、森や林の中、草原など日本各地で見られる野生蘭の一種です。花の大きさは3~3.5cm。名称は春に咲くことからで、栽培されているものも多いです。
シロツリフネ<白釣舟>
高さ50~80cmほど、花冠は長さが3~4cmの筒形。距は後部につき出て、先が渦巻状になります。葉の縁は細かな鋸歯。別名:チョウセンツリフネ。
シロバナタンポポ<白花蒲公英>
タンポポ属の一種で多年生植物。花の大きさは3.5~4.5cmほど、舌状花の花冠は白く、中央の花柱部は黄色で、よく見かける帰化植物のセイヨウタンポポなどと比べ、舌状花が少なく白色なので違いはすぐ分かります。日本在来種。
スハマソウ<洲浜草>
早春、雪解けのあとすぐに開花するため、ミスミソウ、オオミスミソウなどとともに「雪割草」と呼ばれます(良く似ていて区別は難しい)。花は直径1~1.5cmで、色は白のほか、淡紫色やピンクもあります。石川県輪島市(旧門前町)の猿山岬の群落は、特に見事です。
センブリ<千振>
高さ10~30cm、花径は1.5cmほど。花びらは白く、縦に紫色の線があります。日本固有の薬草で、民間薬として使用されていました。「千回振り出してもまだ苦い」ということから名付けられました。
タカネナデシコ<高嶺撫子>
高さ15~40cm、花径約3~4cm。細い茎の先端に花を1~3個つけ、花弁は細かく裂けます。葉も細く、幅2~5mmで全体に粉っぽい白味をおびます。
タカネマツムシソウ<高嶺松虫草>
高さ20~40cm、花径約5cm。キク科の花に形が似ています。葉は対生し、羽状に細かく切れ込んでいます。
タチアザミ<立薊>
高さ1~2m。総苞外片が長く頭花は直立し上向きに咲きます。葉は深く切れ込まず、縁に鋭い鋸歯があります。北海道から本州の主に日本海側に生えます。
タテヤマウツボグサ<立山靫草>
高さ15~30cm、長さ約2.5cmの唇形の花が茎の上部につきます。葉は対生し、柄はないか、あっても短いです。名の靫草は、花穂が矢を入れる靫に似ていることから。
タニウツギ<谷空木>
日本特産の落葉小高木で日本海型気候の山地の谷沿いや斜面に多く見られます。田植えの時期に花が咲くので「田植え花」としても知られています。樹高は2~5m。
タムシバ<田虫葉>
高さ5~10m。花径7~8cm。花弁は6枚、萼片は花弁の2分の1ほどの長さ。コブシによく似ていますが、コブシには開花時に花の下に1枚葉が付いています。
ダケカンバ<岳樺>
落葉高木。シラカンバ(白樺)とよく似ているが、シラカンバよりもさらに高所に分布。樹皮がシラカンバより赤茶色がかっていることや、葉にやや光沢があることでも区別できる。白い樹皮と黄葉のコントラストがきれい。葉の幅は2~7cm。
チングルマ<稚児車>
高さ5~10cm、花径約2cm。花が終わると羽毛状の毛をもつ実ができます。
ツタウルシ<蔦漆>
落葉蔓性木本。主にブナクラス域に分布し、木や岩に絡まり這い登る。紅葉は見事だが毒性が非常に強く、かぶれやすい人は近づいただけでもかゆくなるという。誤って触ったりしないように注意したい。葉の幅は10~20cm。
テガタチドリ<手形千鳥>
高さ20~40cm。幅約8mmの唇形の花が穂状に密集します。花序の長さは5~10cm。名の”手形”は、根が肥大して手の形になることから。
トチノキ<栃の木>
落葉性の高木で高さ25mを超えるものも少なくありません。温帯の落葉広葉樹林の重要な構成種の一つで、木材として、またデンプンやたんぱく質を多く含む実は食用として利用されてきました。葉は大きいもので長さ40cmにもなり、存在感のある紅葉を見せてくれます。ヨーロッパ原産のマロニエはこの近縁種。
ナナカマド<七竈>
バラ科の落葉高木。ブナクラス域までの山地に自生。葉は羽状複葉で皮針形。小さな丸い果実は晩秋に赤く熟し、紅葉とともに美しい。同じバラ科ナナカマド属のウラジロナナカマドは白山など高山帯に分布する落葉低木で、葉の裏が白いことからその名がついた。
ニッコウキスゲ<日光黄菅>
高さ60~80cm、花径約7cm。1本の花茎に3~4花を順に開きます。別名:ゼンテイカ。
ニリンソウ<二輪草>
高さ15~30cm、花径2cmほどの白い花を上向き咲かせます。多くは1本の茎から特徴的に2輪ずつ花茎が伸びるため、二輪草と呼ばれます。葉は猛毒のトリカブトに形が似ています。
ネコノシタ<猫の舌>
葉の大きさや質感が猫の舌にそっくりなのでこの名前がつきました。関東地方、北陸地方以西の海岸の砂丘地などに生える多年草。茎は長く地を這います。別名:ハマグルマ。
ネジバナ<捩花>
湿っていて日当たりの良い草地などに良く生育する。花色は通常桃色で、小さな花が花茎の周りに螺旋状に並んで咲くことからこの名があります。草丈は20~30cm。
ノビネチドリ<延根千鳥>
高さ20~50cm。幅約8mmの唇形の花が穂状につきます。全体的にテガタチドリに似ていますが、唇弁にすじがあり、花序に葉状の苞が目立ちます。また、葉は幅が広く葉脈は明瞭で、縁が波打っています。
ハウチワカエデ<羽団扇楓>
落葉小高木で別名はメイゲツカエデ。葉の幅は5~20cmと大きめで、手のひら状に浅く8~11裂し、重鋸歯がある。天狗が持つ団扇を想像させる。ブナクラス域の山地を中心に分布するほか、庭木などにも用いられる。
ハギ<萩>
高さ50~300cm。花径約1cm。ややしだれた枝の先端から多数の花枝を出し、赤紫や白色の蝶形の花を総状につけます。秋の七草のひとつ。
ハクサンアザミ<白山薊>
高さ0.7~2m、頭花の径約3cm。総苞片は反り返ります。湿った草地に生え、石川・福井・岐阜など白山周辺に固有とされています。
ハクサンイチゲ<白山一華(花)>
高さ20~50cm、花径約2.5cm。白色の花弁のように見えるのは萼片で5~6枚あります。学名のnarcissifloraは「スイセンの花」を意味します。
ハクサンオオバコ<白山大葉子>
高さ7~20cm。穂状につく小花の花冠は白色ですが、萼の先端や突き出た雄しべの葯の赤褐色の方が目立ちます。
ハクサンオミナエシ<白山女郎花>
高さ20~50cm、花径約7mm。花冠は筒状で、先端は5裂し基部の距はふくらむ程度です。岩場や岩礫地に生えます。
ハクサンカメバヒキオコシ<白山亀葉引起>
高さ0.5~1m、長さ約1cmの唇形の花が穂状につきます。葉の先が3裂し、真ん中の頂片が尾状にとがります。名の”亀葉”は葉の形から、”引起”は同属の薬草”ヒキオコシ”からつけられました。
ハクサンコザクラ<白山小桜>
高さ5~15cm、花径約2cm。白山では比較的まとまった群落が各所に見られます。別名:ナンキンコザクラ。
ハクサンサイコ<白山柴胡>
高さ20~80cm、径約1.5mmの小花が10個ほど集まって径約1.5cmの小散形花序をつくり、それがさらに数個集る複散形花序をなします。
ハクサンシャクナゲ<白山石楠花>
高さ0.5~2m、花径約3cm。花は漏斗形で先は5裂、白~淡紅色をおび、内側にうすい緑の斑点があります。葉の裏に褐色の毛があり、縁が裏側に巻くことが多いです。
ハクサンシャジン<白山沙参>
高さ20~50cm。長さ約2cmの釣鐘形の花が数個ずつ2~3段に輪生します。観光新道の馬のたてがみ付近でよく見られます。
ハクサンタイゲキ<白山大戟>
高さ30~60cm。1個の雌しべからなる雄花と1個の雄しべからなる雄花数個でひとゆの花序をなします。黄緑色のものは苞葉といい、2~3枚あります。
ハクサンチドリ<白山千鳥>
高さ10~30cm。幅1.5cmの唇形の花が穂状につきます。萼片と花弁の先が鋭くとがるのが特徴です。葉に紫褐色の斑点があるものをウズラバハクサンチドリといいます。
ハクサントリカブト<白山鳥兜>
高さ0.5~1m。花はたての長さ約3cm。花弁に見える萼片が5枚あり、花弁はその中にあります。葉は3裂しますが、葉柄に達するほど深くはありません。猛毒植物。
ハクサンフウロ<白山風露>
高さ20~50cm。花径約3cm。葉は、掌状に深く5裂し、裂片はさらに細裂します。
ハクサンボウフウ<白山防風>
高さ10~50cm、花径約3mm。花序の径は3~6cm。総苞片も小総苞片も通常ありません。葉は3出複葉で、小葉はミヤマゼンコより大きく形は変化に富んでいます。
ハゼノキ<櫨の木>
樹高は10mほどの落葉小高木。葉は奇数羽状複葉で9~15枚の小葉からなり、小葉は長さ5~12cm。江戸時代に木蝋の原料として琉球王国から持ち込まれたもの。秋には鮮やかに紅葉します。ウルシほどではありませんが、かぶれることもあるので注意が必要です。
ハマエンドウ<浜豌豆>
日本各地の海岸に分布し、日当たりの良い砂地や岩場などでよく見られます。草丈は高くなく、地表面に沿って茎を伸ばし這い広がります。濃紫色のスイートピーに似た愛らしい花を咲かせます。
ハマゴウ<浜栲>
常緑小低木で、茎は地表を這うようにのび、青紫色の小さな花を咲かせます。本州から沖縄、東南アジア、オーストラリアなど広く分布しています。別名:ハマハイ。
ハマダイコン<浜大根>
高さ30~70cm、花径2cmほど。花の色は白く、先端は紅紫に色づきます。根は細く固いので食用になりません。
ハマナス<浜梨>
高さ1~1.5m、花径6~9cmほど。茎に鋭いトゲがあり、花には強い芳香があります。実は梨に似た味でジャムなどにして食べられます。
ハマニガナ<浜苦菜>
ニガナに似た花径3cmほどの黄色い花を咲かせる多年草。海岸の砂地に這うようにして生え、日本および東アジアに広く分布します。別名:ハマイチョウ。
ハマヒルガオ<浜昼顔>
花径4~5cmほど。葉は厚く、光沢があります。砂地で巻き付くものがないので、茎は砂の上を這って広がります。
ハマベノギク<浜辺野菊>
越年あるいは多年草。日本固有亜種で日本海側、富山県以西から九州に分布しています。小枝の先に3~4cmの頭花を一つ付けます。
ハマボウフウ<浜防風>
多年草で食用や漢方薬としても用いられます。ゴボウの様に長い根が伸びます。南西諸島から北海道まで広く分布していますが、海岸の侵食で自生地が著しく減少しています。
ヒメシャガ<姫射干>
花茎の高さは30cm以下。シャガに似てしかも小型であることからこの名前があります。北海道西南部から九州北部まで分布する多年草。山地の樹林下など、やや乾いた場所に生えます。環境省レッドリストの準絶滅危惧。
フジ(ノダフジ)<藤>
花径2cm、花房長20~60cm。中には2m近くになるものもあります。蔓は右巻きで、他の木に巻きついて大きくなります。
フデリンドウ<筆竜胆>
山地の林内や日当たりの良いやや乾いた草原に自生し、花は日が当たっている時だけ開き、曇天、雨天では筆先の形をした蕾となって閉じます。高山植物のタテヤマリンドウ、ミヤマリンドウはフデリンドウの近縁種。越年草で高さは5~10cm。
ブナ<山毛欅>
落葉高木。高さ30mを超える巨木もある。低山の照葉樹林帯と亜高山の針葉樹林帯の間、北陸では「ブナクラス域」と呼ばれるおおよそ標高700m~1500mの間に生え(一部例外もある)、純林に近い見事なブナ林も多い。灰白色樹皮に地衣類などが着いて、独特の模様となる幹と黄葉の林立する様は見事。葉の幅は2~5cm。
マンサク<満作>
高さ2~5m。花径3cmほど。花弁は黄色で細長いねじれたひも状になります。名の由来は”春にいちはやく咲く「まず咲く」から”と”花がたくさんつく様子が「豊年満作」に通じるから”という2説あります。
ミスミソウ<三角草>
高さ10~15cm、花径1~2cm。花弁のように見えるのは萼片で6~9枚あります。葉の形が三角形をしているところから名付けられました。
ミズナラ<水楢>
落葉高木。葉は近縁のコナラと比べ、波打つようなはっきりした鋸歯があり、葉柄がほとんどない。秋に黄色く色づく。その名のとおり水を多く含み乾燥に強く、コナラより標高の高い場所(主にブナクラス域)に生育する。葉の幅は5~10cm。
ミズバショウ<水芭蕉>
高さ10~30cm、花径8~15cm(仏炎苞)。花弁のように見えるのは仏炎苞。水辺に咲き、葉がバショウ(芭蕉)の葉に似ているところから名付けられました。
ミチノクフクジュソウ<陸奥福寿草>
高さ15~30cm、花径3~4cm。花弁は10~15枚、黄色で先端部が赤褐色を帯びています。萼片はほとんど5枚で、長さが花弁の2分の1から3分の2と短いのが特徴です。
ミヤマアカバナ<深山赤花>
高さ5~20cm、花径約8mm。葉は対生し、長さ1~4cm、幅3~12mm。名の赤花は、夏秋の頃葉がよく紅紫色になることから。
ミヤマアキノキリンソウ<深山秋の麒麟草>
高さ20~40cm。頭花の径約1cm。茎の上部に頭花が集まって付きます。名はベンケイソウ科のキリンソウの花に似て、秋に咲くことから。
ミヤマキンバイ<深山金梅>
高さ7~15cm、花径約2cm。葉は縁に粗い鋸歯があり、表面には光沢があります。
ミヤマクワガタ<深山鍬形>
高さ10~20cm、花径約1cm。花冠は深く4裂し、雄しべ2個と雌しべが突き出ます。実のようすが兜の(前立ての)くわ形に似ていることが名の由来です。
ミヤマコゴメグサ<深山小米草>
高さ7~15cm。花は唇形で幅約1cm。下唇が3裂します。葉の上半部に鋸歯があります。名は小さく白い花から。
ミヤマシシウド<深山猪独活>
高さ1~2m、径約4mmの小花が密集する小散形花序が集まり、径20cmにもなる大散形花序をなします。山地帯に生えるシシウドの高山型で、全体的に毛が少なく、葉につやがあるとされています。
ミヤマタンポポ<深山蒲公英>
高さ10~30cm、頭花の径約3~4cm。平地のタンポポより花の色はやや濃いです。総苞は白味を帯び、外片が顕著に反り返ることはありませんが、開出することがあります。(別名:タテヤマタンポポ)
ミヤマダイモンジソウ<深山大文字草>
高さ10~20cm、花径約1.5cm。5枚の花びらのうち、下の2枚が長い。名は花の形を「大」の字に見立てたもの。
ミヤマチドリ<深山千鳥>
高さ10~20cm。花は幅約7mm。距は袋状で約2mmと短いです。葉はふつう2枚で下の葉が大きく、幅約3cmです。
ミヤマママコナ<深山飯子菜>
高さ15~50cm。花は唇形で長さ約2cm。下唇に2つの黄色い斑紋があります。花のつけ根にある葉状の苞には鋸歯がなく、しばしば茎や葉が赤みをおびます。
ミヤマリンドウ<深山竜胆>
高さ5~10cm、花は小さく1.5cmほど。星を連想する青紫の花は、曇った日には閉じます。
モウセンゴケ<毛氈苔>
高さ15cmほど、花径約1cm。食虫植物の一種で、葉に腺毛あり、粘液を分泌して虫を捕獲します。
モミジカラマツ<紅葉唐松>
高さ30~60cm。花径約1cm。花はカラマツソウに似ていますが、葉は掌状に5~9裂し、根元の葉は直径30cmにもなります。
モミジバフウ<紅葉葉楓>
別名、アメリカフウ。北アメリカ中南部から中央アメリカ原産。日本へは大正時代に渡来。街路樹などに利用され、金沢のしいのき迎賓館(旧県庁)と中央公園の間の並木道が有名。
ヤブツバキ<藪椿>
本州から九州に自生する常緑高木で、冬に花が咲くために重宝されます。サザンカとともに古くから品種改良が重ねられ、たくさんの園芸品種が育種されています。
ヤマウルシ<山漆>
落葉小高木。葉軸は赤褐色で目立ち、秋になると葉は紅く色づく。主にブナクラス域に分布し、登山道脇などでも見かけるが、触るとかぶれることがあるので注意したい。葉の幅は2~20cm。
ヤマモミジ<山紅葉>
イロハモミジの亜種または変種、あるいはオオモミジの変種とされる場合もある。イロハモミジより葉は少し大きめ。北陸ではイロハモミジよりヤマモミジの方が多いとされる。ブナクラス域まで分布。
ユキグニミツバツツジ<雪国三葉躑躅>
落葉低木で樹高1~3m。本州の日本海側の多雪地帯に分布しています。紅紫色の花は深く5つに裂け、葉が開く前に咲くので目を引きます。枝先に付ける葉は3枚で、これはミツバツツジの特徴でもあります。
ユキツバキ<雪椿>
常緑低木で、東北地方から北陸地方の日本海側の多雪地帯に適応したヤブツバキの亜種。幹の高さは1~2mほど、ヤブツバキに比べて葉の鋸歯が鋭く、積雪の関係で地を這う樹形になっています。
ユキミバナ<雪見花>
スズムシバナと似ていますが、”常緑である・茎が匍匐する・花茎に開出毛がある”ことなどから、1993年に新種登録されました。滋賀県(北部)から福井県の若狭地方に分布しています。
ヨツバシオガマ<四葉塩竈>
高さ10~30cm。花は長さ約1.5cmで唇形。上唇がくちばし状に鋭くとがります。葉は羽状に切れ込み、通常4枚が輪生するので四葉の名があります。
リュウキンカ<立金花>
高さ15~50cm、花径約2.5cm。花の咲き始めは丈が低く、次第に茎が伸びて高くなります。花弁のように見えるのは萼片。
「みんなでつくる北陸花図鑑」は、みなさんからの投稿写真で構成しています。
あなたの撮った花の写真を投稿してみませんか?
みんなで、自然人ネットならではの「花図鑑」を作りましょう!
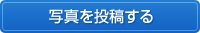
国立公園に指定されている立山・白山では、植物の採取は禁止されています。採取禁止区域でなくとも、採取や盗掘などが自然に与える影響は少なくありません。
「とっていいのは写真だけ」。自然を荒らさないようにこころがけましょう。
また、決められた歩道以外の場所に立ち入ったり、植物を踏みつけたりしないことはもちろん、ゴミは持ち帰るなど、マナーを守って楽しみましょう。
花の名前や解説の間違いにお気づきの方は、編集部へお知らせください







































































































































































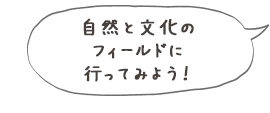

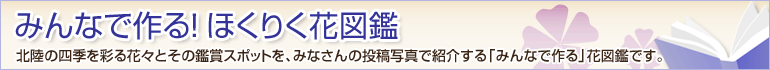



























































































































































 栂 典雅 著「白山・花ガイド(改訂版) 」
栂 典雅 著「白山・花ガイド(改訂版) 」